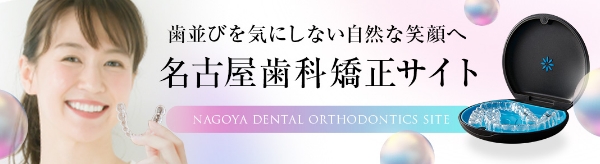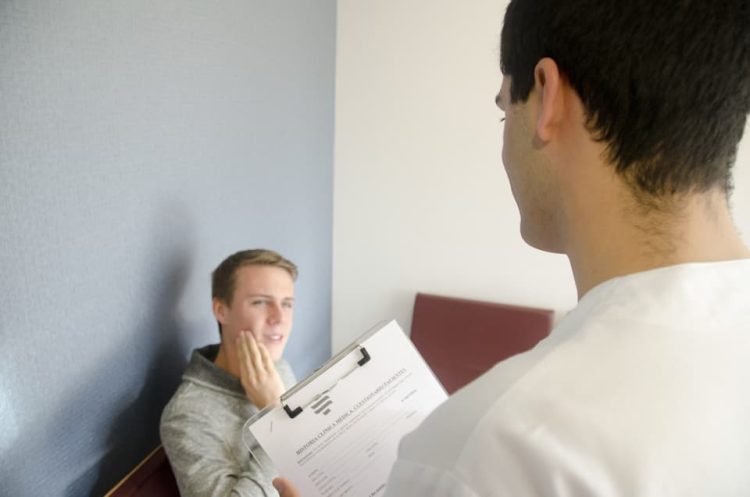歯医者の麻酔はどれくらいの時間効いているのか?

歯医者で治療を受ける際は麻酔を使うケースが多いですが、麻酔が切れるまでどのくらいの時間がかかるのか気になるところです。
治療した場所だけではなく、唇もなんとなくはれているような気がしますし、痺れもあるのでなるべく早く麻酔が切れて欲しいと思う人も多いでしょう。
あらかじめ麻酔がどのくらいの時間効いているのか知っていれば、治療後の過ごし方も考えやすくなります。
そこで、今回は歯医者の麻酔の効力はどのくらい持続するのかを解説します。
歯医者で使用される麻酔について
歯医者で使われている麻酔は大きくわけると①全身麻酔法②局所麻酔法の2種類になります。全身麻酔法は、医療ドラマなどでよく見る、患者の口元にマスクをつけて眠らせる方法です。それに対して局所麻酔法というのは、体の一部分のみに麻酔薬を浸透させることで、その一部分のみ感覚を鈍くさせる麻酔法になります。結論、歯医者では局所麻酔法が最も利用される麻酔法になります。全身麻酔を使用するタイミングというのはいくつかケースがありますが、親知らずの抜歯を含む口腔外科処置やインプラント治療で使用されることが多いです。
そのため、普段の治療で用いられるのは局所麻酔法のため、治療中に眠ったような感覚になることもなく、口元以外で痺れや腫れを感じることはなく、安全性が高い麻酔法になります。
歯医者の麻酔の効き目は短くて10分・長くて6時間程度
歯医者で使われている麻酔の持続時間には、浸潤麻酔法と伝達麻酔法、表面麻酔法の3種類あり、それぞれ効き目の持続時間は異なります。
一般的な浸潤麻酔法の効き目の持続時間は2〜3時間で、伝達麻酔法の場合は4〜6時間です。表面麻酔法であれば、10〜20分ほどで麻酔が切れるでしょう。
歯医者で使われる麻酔方法について

歯医者で使用される3つの麻酔方法がそれぞれどのようなケースで使われるか、その特徴などを解説します。
歯医者で使われる麻酔は、全て局所麻酔で、麻酔が効いている間でも意識を失うことはなく、体の他の部分にも痺れはありません。
浸潤麻酔法
浸潤麻酔法は虫歯の治療から親知らずの抜歯まで、歯医者で幅広く使われる麻酔方法です。
痛みを取り除きたい部分の歯茎に麻酔薬の入った注射をします。注射自体の痛みを軽くするために、細い注射針を使用したり、表面麻酔を行うケースもあります。
浸潤麻酔法の効力は2〜3時間持続しますので、その間の食事は控えてください。また、麻酔の持続時間には個人差があり、一般的な持続時間を過ぎても痺れが残っている場合は、痺れが治るまで食事は控えましょう。
伝達麻酔法
伝達麻酔法は、浸潤麻酔法より広範囲で麻酔を効かせたいときや、麻酔が効きにくいケースで使われる麻酔方法です。
脳とつながっている神経の途中の部分に麻酔をすることで、そこから先の部分の感覚をしびれさせるため麻酔が効き始めるのに時間がかかり、麻酔の持続時間も長めです。
麻酔の持続時間は個人差があり、麻酔が切れるまで半日近くかかるケースもあります。麻酔から覚めるまでは食事は控えましょう。
表面麻酔法
表面麻酔法は麻酔の注射前に注射の痛みを軽減するためや、ぐらぐらの乳歯を抜くときなど軽い麻酔に使われている麻酔方法です。
歯茎に麻酔薬を塗り、歯茎の表面だけ痺れさせます。
表面麻酔法を単体で使用するケースは少なく、ほとんどが浸潤麻酔法の前に使用されています。
歯医者で使われる麻酔薬とは?
歯医者では基本的には局所麻酔法を使用します。その麻酔法で使われる麻酔薬は局所麻酔薬と血管収縮薬の両方が配合されていることがほとんどになります。
局所麻酔薬
昔とは異なり、現在の局所麻酔薬は非常に安全性が高く、アレルギー反応を起こすようなことはほとんどありません。「とは言っても気持ち悪い時が…」という方もいらっしゃいますが、これはアレルギーではなく「治療が怖い」「大丈夫かな」などの緊張感や不安からくる恐怖心などの精神的なものが原因となっていることがほとんどです。
血管収縮薬
局所麻酔法で使われる麻酔薬は、基本的に局所麻酔薬と血管収縮薬を配合して利用されます。なぜ血管収縮薬が配合されているかというと、安全性を高めつつ、麻酔の効きを良くして、麻酔の持続時間を長くするためです。血管収縮薬を配合しているため、局所麻酔の注射をすると注射された周囲の歯ぐきの血管が収縮し、血流が低下します。血流が低下することで結果として、局所麻酔薬がその周囲に広がらずに、かつ麻酔の聞き具合もよくなり、麻酔の注射した部位に留まるようになり、全身に広がらずに済むため安全性が高くなっております。
麻酔が効いている間の食事はケガや火傷の原因になることも
麻酔が効いている間に食事すると、感覚が麻痺しているので、リスクも大変多く、注意が必要です。
よくあるリスクとしては、下記があげられます。
舌や頬を噛んでしまったり傷が悪化する
局所麻酔の場合、口の中の感覚が鈍ってしまい舌や頬を誤って噛んでしまったり、噛んでしまった結果、
噛んだ部分が腫れてしまい、再度噛んでしまうリスクが上がってしまいます。この繰り返しが炎症を起こし、感染リスクが増える原因となってしまいます。
やけどをしてしまう
麻酔が効いているうちは、熱さや冷たさを感じにくくなります。
気づかずにやけどなどを負ってしまい、あとから痛みや炎症を起こしてしまい、
追加治療を行わなければならないケースもあります。
うまく食べ物が飲み込めない
口内の筋肉や舌が麻酔によって感覚が鈍くなり、食べ物を噛んだり飲み物を飲むときの動作がうまくできずに誤嚥をしてしまう可能性があります。
特に小さな子供や高齢者の場合、誤嚥してしまい気管などに食べ物が入ったりすると大きな健康被害をもたらす可能性があるので注意です。
治療の際の痛みや麻酔に不安がある人は治療前に相談しよう
歯医者の治療では、痛みを抑えるために麻酔が使われるのが一般的ですが、麻酔の注射をする痛みも不安な人や、長時間麻酔が続くことに不安を感じる人は治療前に歯科医に相談をおすすめします。
歯医者によっては対応が難しいケースもあるでしょうが、痛みや不安を我慢する前にまずは相談しましょう。
麻酔の注射の痛みが不安な人には、麻酔薬注入時の角度や圧力をコンピューター制御した電動注射筒を使用したり、事前に使用する表面麻酔剤も自分頃のみの香りを選んで少しでもリラックスできるような対応が可能な歯科医もあります。
名古屋歯科は診断と治療において根拠に基づいた考え方を徹底し、患者の要望に柔軟に対応してくれるので、おすすめです。
歯医者の麻酔は治療に応じて種類が異なり、麻酔が効いている間は食事NG
歯医者で使用される麻酔は治療内容に応じて種類が異なり、その効力の持続時間も違う上に個人差もあります。
一般的な麻酔の持続時間は2〜6時間程度です。
また、麻酔が効いている間はぬるめの飲み物を、口内に負担をかけない程度の少量で飲む程度にしておくと安全です。
麻酔が切れてきたら下記を参考に食事を楽しんでください。
熱いものは避ける
先述通り、熱いものは避けましょう。まだ感覚が鈍っている可能性があるので、ぬるい飲み物や、冷えた食べ物のほうが口内への負担は少ないです。
やわらかい食べ物を選ぶ
お粥やスープ、ヨーグルト、お豆腐などのやわらかい食べ物がおすすめです。
治療した歯や口内に負担をかけないようにしましょう。
常温のお茶や冷えたお水を飲みましょう
刺激性の強い飲み物は口内への負担も大きいため、コーヒーやアルコールなどはできるだけ控えましょう。また、ストローは抜歯や治療後の口内への負担も大きいので控えましょう。
名古屋歯科では、麻酔の際にコンピューター制御の電動注射筒や5種類の香りの中から選べる表面麻酔薬を使用するなど、患者様にとって安心して治療を受けるために柔軟な対応をしています。歯医者での麻酔治療に不安がある方は名古屋駅・名駅から徒歩5分の名古屋歯科名古屋駅院にお越しください。